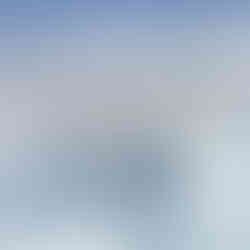知識があっても「言語化」に戸惑う学生が増えている実態|大学の教育現場から解説

大学で英語教育に携わる中で、近年、ある共通した傾向を感じています。
それは、単語や文法などの知識は豊富なのに、「説明」となるとアウトプットに壁を感じてしまう学生が多いという点です。彼らは英語の知識を持っていますが、「何を書けばいいのか」「どう論理立てて伝えるか」という発信の段階で戸惑ってしまうのです。
この傾向は、特に複雑なデータや結果を扱う場面で顕著になります。これは英語力そのものの問題というよりも、データを論理的に言語化し、人に説明する訓練(アウトプットの経験)を積んできたかどうかの違いではないかと考えています。
工学部の英語授業で見えた学生の「言語化への壁」
工学部の授業で、グラフやデータを英語で説明する課題を出しました。 使用したのは、数値が明確なパイチャート(円グラフ)や折れ線グラフなど、比較的シンプルな資料です。しかし、課題開始直後、教室には戸惑いの空気が流れました。多くの学生の手が止まり、以下の点で立ち止まっていました。
数字は見えている:データの増減や大小関係は把握している。
何が起きているかも分かっている:グラフが示す「結果」は理解している。
それを文章としてアウトプットできない:英語で事実を淡々と書く作業で手が止まる。
彼らにとっての課題は、グラフやデータを英語で表現するためのライティング経験が圧倒的に不足していることでした。特に、変動や割合を示す適切な表現を知らない、または使う練習をしたことがないことが原因でした。
そこで、指導を「説明を促す質問」に変え、同時に表現の基礎を提供しました。
「増えていますか? 減っていますか?」
「一番大きな変化はどこですか?」
「全体の何割を占めていますか?」
この問いかけと、それに付随する定型表現の導入により、学生たちは少しずつ「言葉」として事実を抽出し、書き始めることができるようになりました。これは、「ライティング経験と表現知識の不足」こそが、学生たちの「言語化への壁」であったことを示しています。

英語の知識は十分。次のステップは「論理的に説明する経験」
この授業を通して明確になったのは、学生たちが持つ知識を「使える力」に変える経験が不足しているという点です。これは日本語でも同じです。データや実験結果を「分かったつもり」になることは簡単ですが、それを他者に正確に伝える機会は意外と少ないものです。
英語というツールを使うことで、この「アウトプット力・説明力の伸びしろ」がよりはっきり浮き彫りになります。理系・文系問わず、事実や意見を正確に伝える力は、グローバルな現場で必須のスキルです。
従来の英語教育が抱える課題|「文系主体」の学習への危惧
従来の日本の英語教育は、文学作品の読解や、文法規則の暗記など、どちらかというと「文系科目」としての側面に重点を置く傾向がありました。
その結果、「論理やデータを客観的に扱うための英語」の訓練が手薄になりがちでした。つまり、文脈を理解する力は育っても、事実を論理的に整理し、それを言語化して伝える力(アカデミックやビジネス英語で最も重要とされる力)が不足しているのです。
理系・文系を問わず、実社会で求められるのは、まさにこの「論理や事実に基づいた説明能力」です。
データを英語で説明する際に必須の表現
実社会でデータを英語で説明する際、求められるのは華麗な表現ではありません。事実を正確かつ簡潔に伝える表現です。
授業で扱った、理工系の学習やデータサイエンスの基礎となる具体的な英語表現の例を紹介します。
1. 割合を表す英語(パイチャート)
a quarter / one fourth(4分の1)
approximately half(約半分)
a majority of(大部分)
例文: A quarter of the total output comes from renewable energy sources.
2. 増える・減るを表す英語(グラフの比較)
increase / decrease
rise / fall
例文: The number of users increased over time. In contrast, energy consumption decreased.
3. 急激な変化を表す英語(出力・数値の変動)
skyrocket / plummet(急上昇・急落)
fluctuate(変動する)
maintain(維持する)
例文: The system output skyrocketed after the update. Production plummeted during the shutdown.

実務経験から感じた「説明できる英語力」の重要性
以前、医療機器メーカーで働いていた際、英語でやり取りをする相手は、主に医師やエンジニアでした。
その場で彼らが求めていたのは、流暢な会話や難しいイディオムではありません。彼らが求めていたのは、数字や実験結果を正確に、論理的に説明できることでした。
現在、大学で学生を指導していると、当時の現場で求められていた「事実を言語化する力」と、学生に不足している力が完全に一致していると感じています。
英語学習で本当に身につけたい「理系・文系を問わない力」とは
英語学習の目標を「流暢に話せるようになること」に設定しがちですが、実社会で本当に求められるのは、以下の要素を順序立てて説明できる力です。
何が起きているのか(事実)
どこが他のデータと違うのか(比較・対照)
なぜそう言えるのか(根拠・論拠)
英語は、単なる科目ではなく、この論理的な思考と説明する力を可視化するための強力な道具なのです。

メルク英語教室が大切にしている「説明できる英語」の理念
メルク英語教室では、単に正解を選ぶための英語学習だけでなく、自分の考えや結果を相手に伝えられる「説明できる英語」を大切な要素の一つとして捉えています。
特に高校生のクラスでは、新聞記事の読解やデータ分析を通じた意見交換を行い、数字や事実から論理的に言語化する練習を取り入れています。
この力は、お子さまが将来、理系・文系を問わず、社会で活躍するための揺るぎない土台となります。
私たちは、英語は目的ではなく、「考えを形にし、相手に届けるための手段」であると考えています。